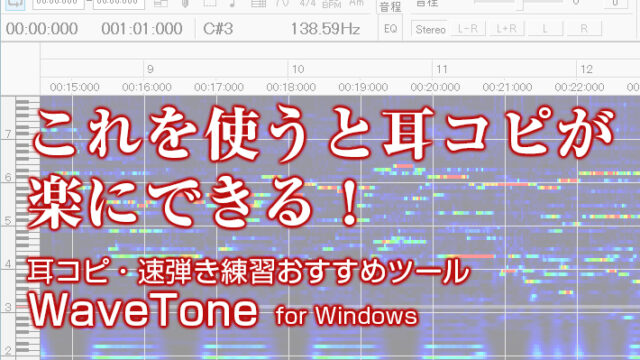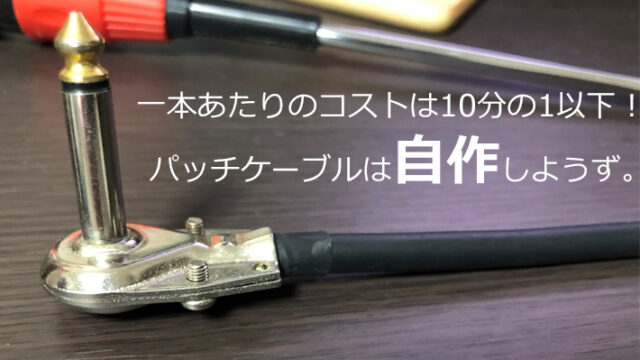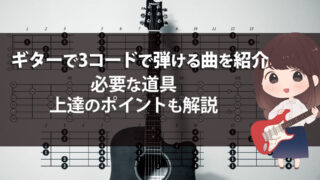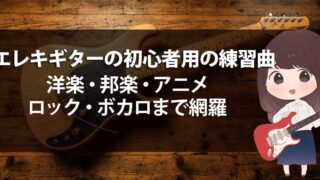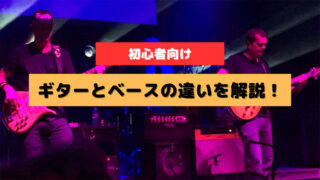いろいろ試してみて、なんとなくG3n(G3Xn)の使い方がわかってきましたので音作りのコツを書いておきたいと思います。
今回のお話では、アンプのリターンにさす事を前提としたいと思います。そして作る音は個人的な嗜好でゲイン高めなドライブサウンドとします。よく使うアンプはJC-120です。。。
まず最初に音作りに影響するG3n(G3Xn)の特徴をまとめます。
G3n(G3Xn)の特徴1 マスターボリュームで音質が変わる
アンプのリターン端子に繋いだ場合、G3n(G3Xn)のマスターボリュームが出音の音量を決める最終的なツマミになり、0~120の間で設定するのですが、聞こえ方として「音が大きくなる」というよりも「よく聞こえてくる」といった感じがします。
わかり辛いですかね(;´Д`)
私の印象ですが、例えば30と50で“音量”にそんなに大差がないように感じます。ただ、ボリュームを上げると高音が強調、もう少し別の言い方をすると音が抜けてきてよく聞こえるようになってくる感じです。
そして一定値を超えてくると、潰れて詰まってきます。
だからマスター上げたらトレブルを下げる、こもってたらトレブルを上げるのではなくマスターを上げるとかいう操作も試してみるといいかと思います。
G3n(G3Xn)の特徴2 キャビシミュは必須
今まで使った事のあるPODなどのアンシミュ有りのマルチでは、アンプにさすときはキャビシミュを切るのが当たり前な感じでしたが、G3n(G3Xn)はどんなセッティングでもキャビシミュ入れないと音がまとまらないようです。そしてマイクもONにした方がいい場合が多いように感じます。
G3n(G3Xn)の特徴3 ブースターも必須
私が良く使うアンプモデリングはJCM800、ボグナー、MESA RECTI、DIEZELですが、アンプ単体でゲインを上げると低音の抜けが悪くて潰れてきます。ですので、アンプのゲインは1時~2時くらいにとどめておき、前段にODを入れます。
OD挿すだけで大体音抜けは解決しますね。中でもお気に入りはGoldDriveです。
OD挿した時のデフォルト設定で十分なのですが、それで歪み過ぎてたらアンプのゲインを下げていく事で低音弦をミュートした時の立ち上がりをコントロールしてます。
G3n(G3Xn)の特徴4 基本的にこもりがち
OD→アンシミュ→キャビシミュという流れは必須なのですが、いまいち高音が足りないと感じる事が多くあります。それでアンプのトレブルを上げるのですが、利きが悪いかそこじゃないと感じる周波数帯が出てしまう場合が多々あるので、その場合はキャビシミュの“Hi”をガツンと上げるか、マイクがONなら57側に寄せると大体思ったような抜け方をしてきます。
これでも足りないという場合は特徴1で言ってたマスターを上げるかですね。
G3n(G3Xn)の特徴5 キャビはなんだかんだヘッドとセットがいい
アンプとキャビは別々に選べますが、ドライブサウンドを作る際はヘッドに合わせたキャビを選ぶのが一番まとまります。それ以外だとマーシャルの4×12は比較的どれとも合う気がしますが、いろいろ変えてみてアンプとセットなキャビにしたときが一番しっくりきますね。
音作りのフロー
1.アンプとキャビを選ぶ
ここで音質を詰めていくような事はあまりしません。欲しい音のキャラクターに近いアンプを選んで、ざっくりと調整します。
キャビのマイクは大幅に音が変わりますので、ON/OFFでどちらが理想の音に近いかで選んでおきます。大体ONです。
この機種はこもっている音を抜けさせるよりも高音過多な物を丸めて行く方が楽だと感じてます。
2.ODを刺す
アンプのキャラクターをあまり変えず、ゲインプッシュしてくれるような機種がいいのでTS DriveやRC Boost、Gold Driveを選ぶ事が多いです。
特に音のこもりが気になる時はGold Driveを入れる事でカリっと明るくなってくれるので重宝してます。
3.アンプでゲイン調整
ほとんどの場合、ODを入れると歪み過ぎになりますので、アンプのゲインを下げます。
ODのレベルやゲインでも歪み方の調整はもちろん可能ですが、音質を維持したまま歪みの量を減らしたい場合はアンプの方を触る方が扱いやすいかと思います。
4.キャビでイコライジング
イコライジングはアンプでやりがちですが、G3n(G3Xn)の場合はキャビのHi/Lowの方が効き方が素直です。アンプのトレブルは「ジー」とか「ミー」とかいう当たりだけが上がるので、最終的な微調整でしか触っていません。
マイクがONの場合…というかほとんどONで使ってますが、SM57とMD421のバランスで質感調整します。57に寄せるとカリっとしてきて421に寄せるとザラっとしてくるイメージ。
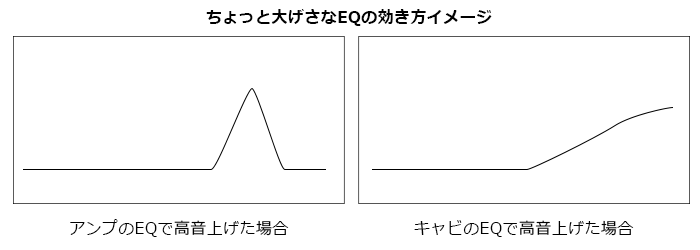
5.後はお好きなエフェクトを
なんだかんだZNR(ノイズリダクション)は入れますけどね。そうなるとあと2個しか入れられませんけども(;´Д`)
私はON/OFF想定のディレイと常時かけっぱなしのリバーブ(EarlyRef)を入れてます。
6.並べ替え
パッチの切り替えではなく、エフェクトのON/OFFで使う事が多いので、操作上並べ方が重要になってきます。操作できるのは横並びの3つなので。
普通ならOD→AMP→CAB→ZNR→DLY→REVとしたい所ですが、
OD→AMP→ZNR→DLY→REV→CABとしてます。
こうする事でON/OFF操作を行うアンプのレベルブーストとディレイが同一画面上に出てきますので、左右の移動をしなくてすみます。
以上。ちょっとクセがあっていい音作るのにコツがいると思いますが、詰めきった時のポテンシャルは高いのではないでしょうか。
買って初めてプリセットの音出した時は正直言ってすぐ売ろうかと思いましたが(笑)
誰でも簡単手軽にという感じはしませんが、それなりに満足いく音は作れました。
この記事見て面倒くせーなと思った人はBOSSのGT-1がいいと思います(笑)
そういったときは、楽器店の下取りに持ち込んでも良いのですが、やはり重たい楽器ともなると、持って行くのも少し面倒だったりするもの。
そんなときにオススメなのが、ネットからも申し込める楽器買取店。
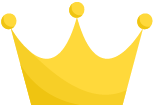 楽器の買取屋さん
楽器の買取屋さん2.ギター買取以外にもベースやギターなどどんな楽器でも買取可能!
3.宅配買取でも送料・手数料完全無料!
電話でもネットでも申し込みができ、最短30分で楽器を現金化できるという圧倒的なスピードが魅力的。
また、査定も楽器のプロが行いますし、全国対応の安心感もあります。
楽器の下取り・買い取りを検討されておられる方、ぜひネットからの楽器下取り・買い取りにチャレンジしてみてください!
| 評価 | |
|---|---|
| 名前 | 楽器の買取屋さん |
| 特徴 | 出張買取・即日対応・宅配買取・全国対応 |
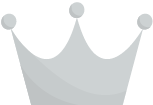 楽器の買取【バイセル】
楽器の買取【バイセル】2.送料無料!箱に詰めて送るだけ♪バイセルの宅配買取
3.楽器以外の時計やブランド品も買取しています。
ギター・管楽器・弦楽器など経験豊富なスタッフがしっかりと状態を確認します。
| 評価 | |
|---|---|
| 名前 | バイセル |
| 特徴 | 出張買取・即日対応・宅配買取・店頭買取 |